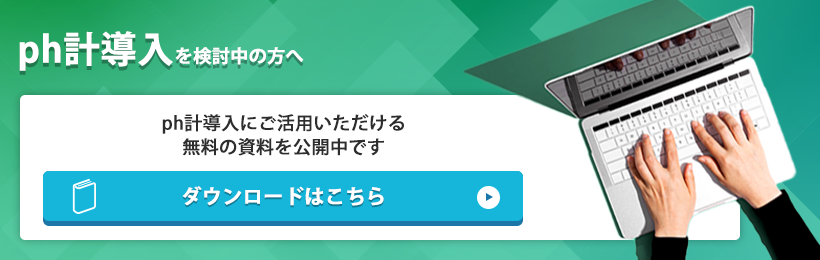水質検査の10項目・11項目の違いは?検査義務対象も紹介

私たちが毎日使用する日本の水のほとんどは安全が確保されています。
しかし、過去・現在問わず水質汚染事故が発生しているのも事実です。
人体に影響を与えず安全・安心に暮らしていくために、水質検査は非常に重要だと言えます。
法律で定められた水質検査の実施項目として、51項目・16項目・11項目・10項目がありますが、今回は10項目・11項目に焦点を当てて解説します。
10項目と11項目の違いは何なのかをはじめ、各項目の内容、水質検査に関する法律、検査頻度まで解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
水質検査とは?

そもそも水質検査とは何なのでしょうか。
水質検査の種類もあわせて解説します。
水質検査の役割
水質検査は、私たち人々が使用する水が安全・清潔に使用できる基準に達しているかを調べる目的で実施します。
水の色・ニオイをはじめ、微生物・細菌など化学物質の有無まで検査を行います。
検査項目・基準は水の使用用途によって異なるため、すべてが同じ基準ではありません。
検査で基準に満たない水を使用すると、社会・生活で大きな影響が生じてしまいます。
実際、水道水での病原大腸菌(O121)による水質汚染事故や、上水道での軽油による水質汚染事故が発生しています。
私たちの健康のために非常な検査であるため、水道業者には水質検査が義務付けられているのです。
参考:厚生労働省「水質汚染事故等の発生状況」
水質検査の詳細については、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:水質検査の方法とは?用途や種類別の特徴を把握しよう
水質検査の種類
水質検査には、
- ・飲料水水質検査
- ・一般遊泳用プールの水質検査
- ・公衆浴場の水質検査
があります。
まず飲料水水質検査の検査項目は、水道法では51項目、建築物衛生法では16項目・消毒副生成物12項目を行わなければなりません。
次に一般遊泳用プールの水質検査では、厚生労働省が定めた「遊泳用プールの衛生基準について」により7項目を行う必要があります。
最後に公衆浴場の水質検査は、厚生労働省が定めた「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」にて指針が表記されています。
それぞれ規定された項目を確認し、指示通りに検査を行いましょう。
水質検査に関する法律
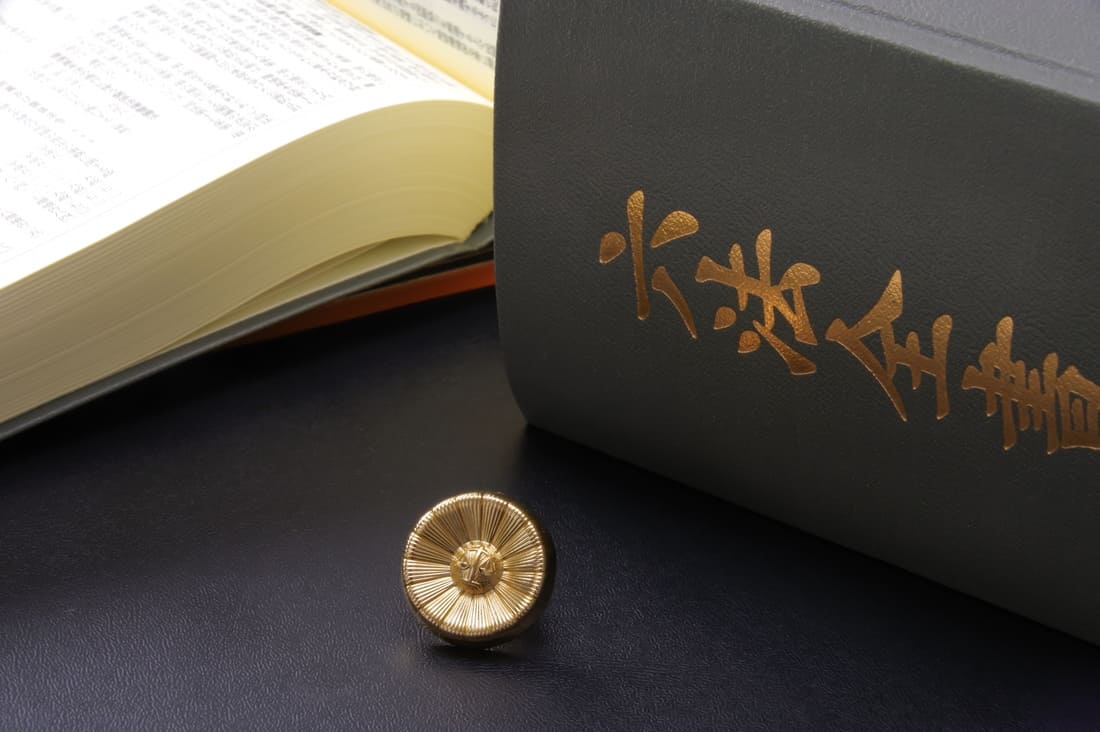
水質検査は水道法に基づいて行わなければなりません。
水道法の第20条では、以下の内容が表記されています。
- ・水道事業者は定期・臨時で水質検査を行わなければならない
- ・水質検査を行った場合は、記録を作成し5年間保存しなければならない
- ・水質検査に必要な検査施設を設ける必要があります。ただし、地方公共団体の機関や厚生労働大臣の登録を受けた事業者に委託する場合は設ける必要はない。
これら以外にも、厚生労働大臣の登録基準や、受託義務、水質検査機関の規定などが表記されていますので、確認しておきましょう。
参考:水道法第20条
水質検査内の10項目・11項目の違い
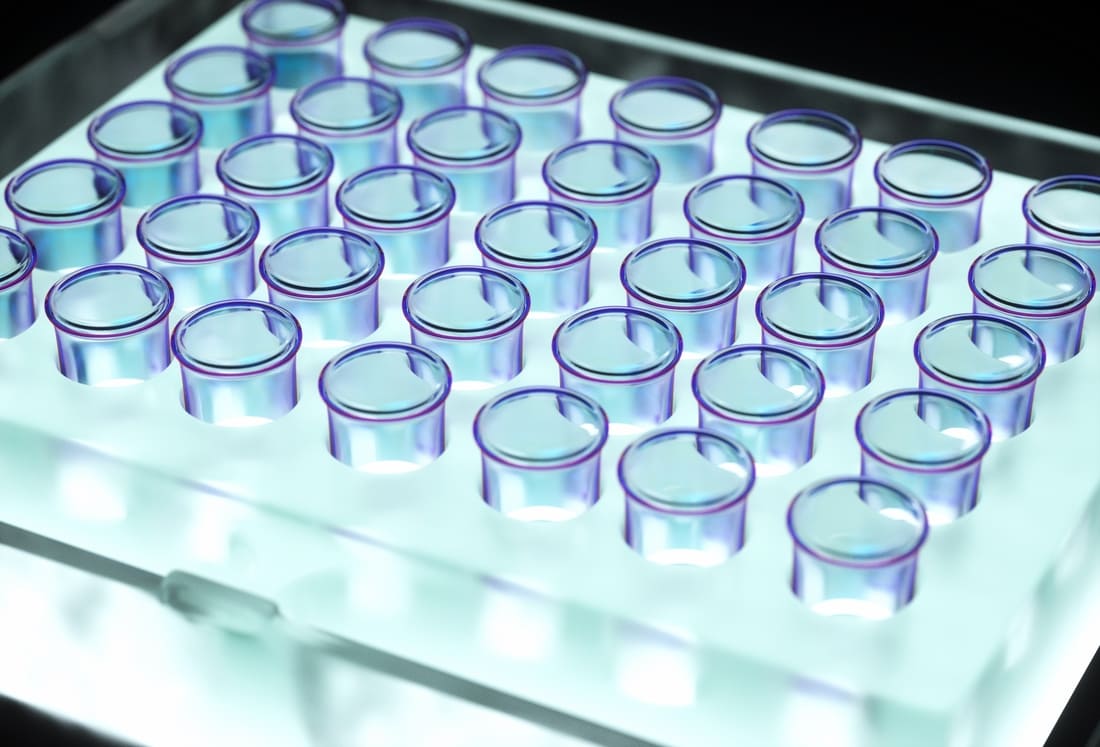
水質検査には、10項目と11項目があります。
違いは何なのでしょうか。
内容もあわせて解説します。
10項目の内容
昭和32年に公布された水道法内の水質検査では、10項目の検査が必須となっています。
では、10項目の内容と基準値を紹介します。
| 項目 | 基準値 |
| 一般細菌 | 100CFU/mL以下 |
| 大腸菌 | 検出されない |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
| pH値 | 5.8~8.6 |
| 味 | 異常ではない |
| 臭気 | 異常ではない |
| 色度 | 5度以下 |
| 濁度 |
2度以下 |
では、それぞれの検査項目の意味を解説します。
一般細菌
一般細菌とは、標準寒天培地で36℃かつ24時間で培養した時に検出される細菌の集合体のことです。
一般細菌内にはさまざまな菌があるため、川や土壌、食品、空気中などに含まれる無害の菌もあります。
しかし、人体に害を与える病原性大腸菌も含まれているのです。
病原性大腸菌が体内に入ると、下痢や激しい腹痛などの症状が生まれ、場合によっては重篤な合併症により死亡する可能性もあります。
汚染の原因となるのは、水道水の場合汚水・異物が混ざってしまったり、タンクの汚れ・残留塩素がなくなっていたりすることです。
井戸水の場合は汚水の混ざりや消毒設備の故障、降雨の影響で汚染の原因となります。
場合によっては、蛇口や除水器に細菌がたまっていることが原因となる場合もあるので注意が必要です。
汚染している水には多くの一般細菌が含まれていることから、水の汚染状態をチェックする目安となります。
一般細菌の基準が超えている場合は、生水を飲んではいけません。
また、プールにも使用できませんので注意してください。
大腸菌
大腸菌とは人間や動物の体内に存在する腸内細菌のひとつです。
ほとんどの大腸菌は無害ですが、大腸菌の中には病原性大腸菌・下痢原性大腸菌と呼ばれるものがあり、人体に害を与えてしまいます。
適切な処理を行っていると検出されることはありませんが、汚染していた場合・異物が混ざっていた場合に検査が不合格となります。
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
硝酸態窒素とは、空気や土壌、水中に含まれる窒素のことです。
多くの植物・農作物の肥料のひとつとして使われているため、水に肥料が混ざった場合や動植物が腐敗した場合などが原因で発生します。
生活排水や工場排水が適切に処理されていない場合も検出されます。
亜硝酸態窒素とは、食品発色剤によく使用される亜硝酸塩中の窒素のことです。
硝酸態窒素と同じく、肥料や腐敗した動植物、下水などに含まれたことが原因で検出されます。
皮膚や粘膜が青紫色に変化するチアノーゼ症状や呼吸困難を引き起こしてしまい、人体に大きな影響を与えてしまいます。
塩化物イオン
塩化物イオンとは、ナトリウム塩、カリウム塩などの塩化物が水に溶けだしている塩素分のことです。
下水・排水・海水などが混ざったことが原因で検出されます。
自然界の水には少しの塩化物イオンが含まれていますが、屎尿や下水には多くの量が含まれています。
そのため、汚染の指針とされているのです。
有機物(全有機炭素(TOC)の量)
生活排水や産業・工業排水などが原因で発生する有機物は、水を汚染してしまいます。
川が濁っているのも、有機物が原因です。
排水以外にも、生物の繁殖により有機物量が多くなると言われています。
pH値
pH値は水が酸性・アルカリ性のどちらなのかを示すものです。
汚染していない際にはpH値は安定していますが、汚水や藻の発生、薬品の多量注入などによって変化してしまいます。
水質検査の基準となり、水質の変化・腐食・水処理による影響などを測ることが可能です。
味
不純物や微生物が発生していると、味が変化します。
味の変化は異常・危険な状態を表します。
水道水では汚水や異常物質が混ざったり、配管が腐食していると味が変化し、
井戸水では藻の発生や硫化水素が原因で発生します。
臭気
味の変化と同じく、不純物が含まれていたり微生物が発生すると異常な臭いが出てきます。
正常な水でも少し塩素の臭いがすることもありますが、水道水処理の中で塩素を使うため問題ありません。
色度
色がついている場合は汚染されていると判断されます。
鉄や亜鉛などの金属や有機物が含まれていたり、汚水が混ざっていたりすることが原因で発生します。
濁度
汚染状況や水処理の効果を測る役割をもつのが、水の濁りです。
施設内の配管が洗浄されていなかったり、生物が繁殖していたり、設備が壊れていたりして濁ってしまいます。
井戸水の場合でも、鉄分の含みや酸化により発生します。
11項目の内容
11項目では、亜硝酸態窒素の単体で検査することが必要です。
前述の通り、肥料や腐敗した動植物、下水などに亜硝酸態窒素が含まれると、メトヘモグロビン血症等を引き起こす原因になるなど、人体に大きな影響を与えてしまいます。
特に乳幼児には大きな健康被害を生みます。
法令改正で省略できない項目が11に増えた
前述の通り、飲料水水質検査の検査項目は、水道法では51項目、建築物衛生法では16項目です。
しかし、検査に合格した場合、次回検査に限り項目を省略できます。
平成26年4月1日に施行された法律により、省略できる項目が10項目から11項目へと変更になりました。
ただし、法令・条例にかかわらない水質検査では10項目が活用可能です。
簡易に水質検査ができる項目として、簡易専用水道、小規模貯水槽水道、一般家庭の直結給水などがあります。
11項目の水質検査頻度について

11項目の水質検査頻度は以下の通りです。
| 項目 | 検査頻度 |
| 一般細菌 | 1か月に1回以上 |
| 大腸菌 | |
| 塩化物イオン | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | |
| pH値 | |
| 味 | |
| 臭気 | |
| 色度 | |
| 濁度 | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 3か月に1回以上 |
| 亜硝酸態窒素 |
水質検査が義務付けられている対象

特定建築物にあてはまる建物は水質検査が義務付けられています。
義務対象の建築物は以下の通りです。
| 建築物 | 延べ面積 |
| 百貨店 | 3,000㎡ |
| 図書館 | |
| 遊技場 | |
| 美術館 | |
| 博物館 | |
| 興行場 | |
| 店舗 | |
| 事務所 | |
| 規定する学校以外の学校 | |
| 規定する学校 | 8,000㎡ |
まとめ:水の安全性確保のために法を遵守し定期的な水質検査を行うこと

私たちが日々使用する水は、安全性を確保しなければいけません。
水質汚染は水道管が劣化も1つの原因です。
そのため、現在ではあらゆる建物で大規模修繕が行われています。
水の安全性を確保し人々の生活・健康を守るためには、修繕だけに頼るのではなく定期的な水質検査を行う必要があります。
過去に水質汚染が原因でタイイタイ病や水俣病が発生したように、安全・清潔でない場合は、人体に大きな影響を及ぼしますよね。
近年でも、2022年に小規模貯水槽水道での一般細菌、大腸菌による水質汚染事故、
2021年には 専用水道で亜硝酸態窒素による水質汚染事故が発生しています。
傷ましい事故が起こさないためにも、法を遵守して定期的な水質検査を行いましょう。